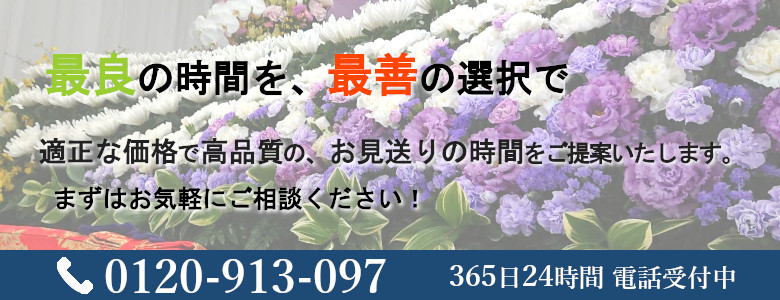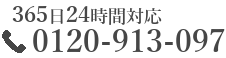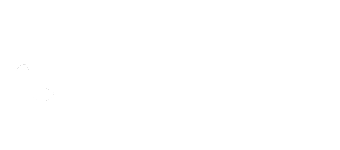万が一のとき
在宅医療または傷病があり通院していた方がご自宅で亡くなった場合
継続的に診てもらっているかかりつけ医に連絡をしましょう。
来診で「生前に診療していた傷病に関連する死亡である」と認められると死亡診断書が交付されます。
老衰のお年寄りなどは、医師が来ないうちにご家族が見守る中で息を引き取る場合があります。その際は、臨終に立ち会ったご家族が故人様に末期の水を行います。
事故死や突然死、自殺の場合
遺体に手を触れずに至急警察に連絡をしましょう。
警察医や監察医による検死が必要となります。
死因が特定できれば遺体はご家族に引き渡され、死体検案書が交付されます。
死因が特定できなければ行政解剖を行う場合があり、死因の特定には時間がかかる可能性もあります。
病院で亡くなった場合
医師より危篤であると宣告されましたら、最期に会わせたい身内などへ至急連絡をとり、医師や看護師の指示に従いましょう。
死亡が確認されると死亡診断書が交付されます。
臨終の際には、立ち会った全員で末期の水を行います。
ご臨終から数時間以内に病院を出なければいけないため、遺体の清拭は看護師に任せ、故人様をお連れする場所の準備をしなければなりません。
葬儀社に連絡をして自宅もしくは安置施設に行きます。
ポイント
- 死亡診断書・死体検案書について
- 死亡診断書や死体検案書は、死亡届と一体の用紙となっております。この書類を役所に提出し、受理されると火葬許可証が発行され、火葬や納骨の手続きができます。
ご自宅で亡くなった場合や突然死の場合、死亡診断書や死体検案書はその場ですぐに交付されません。交付されてから葬儀社へ連絡しましょう。
また、この書類は金融機関・生命保険会社・相続の手続き等でも必要な書類のため、役所に提出する前に5~10枚ほどコピーをしておくと良いです。
- 末期の水(まつごのみず)とは
- お葬式における最初の儀式です。
「安らかに旅立って欲しいという願いを込めて行った」という説や、「故人に生き返って欲しいという願いを込めて行った」という説、「神道で死者の穢れを清めるために行った」という説など末期の水の由来は諸説唱えられていますが、いずれにしても長い歴史の中で日本人の生活に深く根付いた儀式であるといえるでしょう。
末期の水は、新しい割り箸の先にガーゼや脱脂綿をくくりつけ、それに水を含ませて故人の唇を湿らせます。
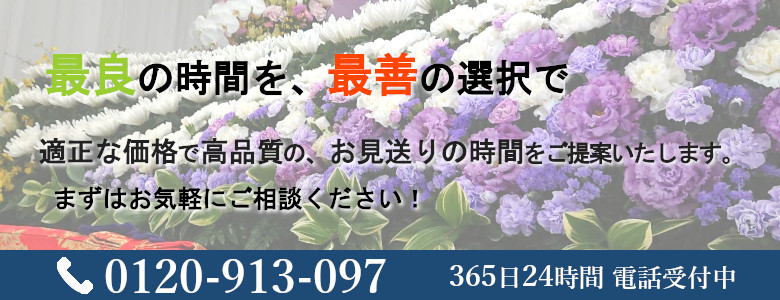
喪主の決め方
故人の遺言で喪主の指定がない場合、一般的には配偶者が喪主を務めます。
配偶者が喪主を務めることが困難な場合は、血縁者が喪主を務めます。
具体的な優先順位は、故人の長男、次男以降の直系の男性、長女、長女以降の直系の女性、故人の両親、故人の兄弟姉妹となります。
故人に配偶者や血縁者がいないときには、友人や知人が喪主を務めても問題ありません。
喪主になったらやること
葬儀前
- ご遺体の搬送先を決めて依頼
- 葬儀社手配
- 死亡診断書の受領
- 病院治療費等の精算
- 役所へ死亡届提出
- 寺院連絡(必要に応じて)
葬儀中
- ご遺族様の代表挨拶
お葬式の形式によって異なりますが、主に「通夜挨拶」「出棺挨拶」「お斎(おとき)挨拶」と3回の挨拶を行います。
- 通夜挨拶
- 通夜の参列者様へ向けた挨拶
- 出棺挨拶
- 出棺をお見送りされる方へ向けた挨拶
- お斎挨拶
- お斎(精進料理)を召し上がる前に行う挨拶
葬儀後
- 後飾りの設置
- 香典返しの手配
- 仏壇・位牌・お墓の準備(必要に応じて)
- 四十九日法要の手配(必要に応じて)
葬儀場の選び方
- セレモニーホール
- 立地や設備が充実しているが、混雑により葬儀まで期間が空く可能性がある
- 公営の葬儀場
- 公営の葬儀場は費用が抑えられる一方で、混雑や立地を考慮する必要がある
- ご自宅
- ご自宅は心理的にご家族様にとって最も落ち着く空間ですが、煩雑な準備や周辺住民への配慮が必要となる
- 寺院
- 本堂の葬儀は格式の高いお葬式を執り行う事ができる一方で、檀家しか使用することができない
- ホテル
- 多目的空間を十分に設けているホテルもあり立地・設備は充実しているが、高額になる可能性がある
お葬式の事前準備
- 遺族の心構え
- 悲しみに暮れる暇なく、通夜・葬儀の手配に遺族は慌ただしい時を過ごさなければなりません。
心身を労することになりますから、気をしっかり持って、故人様への最期のお務めを果たしましょう。
- ご遺体の安置場所
- 一般的には病室から遺体安置所に移りますが、葬儀場やご自宅での安置も可能です。
ご自宅での安置は、低温に保つ適切な環境設備が必要となります。
- 喪主の決定
- 葬儀内容を取りまとめ、会葬者やご僧侶への対応等重要な役割を担います。
- 信仰の確認
- 日本でお葬式に関わる宗教は、多いものから「仏式」「神式」「キリスト教式」「無宗教式」に分かれます。世代や地域によっては重要な要素となりますので、ご家族様による十分な確認が必要です。
- 葬儀会場・葬儀社の選定
- 病院が葬儀社を紹介してくれることもありますが、依頼内容が不明瞭となるケースが多く、その後に金銭や契約トラブルが生じる事もあります。病院から紹介された葬儀社を断ることは失礼にはなりませんので、すぐに決めずに落ち着いてしっかりと判断し、信頼のおける葬儀社に依頼しましょう。
- 葬儀形式の決定
- 葬儀形式は「火葬式」「一日葬」「家族葬」「自宅葬」「一般葬」「社葬」など様々です。それぞれに向き・不向きがありますので、故人様・ご家族様のご意向を反映できる形式を選びましょう。
- 訃報の通知
- 葬儀の日程が決まった後、親戚や友人、勤務先やその他の関係者に連絡をします。
- お手伝いの依頼
- 受付等のお手伝いが必要な場合は、親戚・町内会・組合等に依頼をしましょう。
火葬までの流れ
ご逝去
逝去(せいきょ)とは、家族など身内以外の他人の死について表現する際に使用します。
死亡診断書または死体検案書を受け取り、安置場所までの搬送手配をします。
ご安置
安置(あんち)とは、息を引き取ってから納棺までの間ご遺体を置いておくことを言います。
安置場所は、ご自宅・斎場や葬儀社の霊安室・民間業者の霊安室などがあります。
亡くなった場所(病院・警察・自宅)からご希望の安置場所までお連れします。
故人様の頭を北方面に向けて安置し、神棚に半紙を張ります。
喪主は布団の準備・弔問客の対応を行います。
お通夜
通夜(つや)とは、遺族や親類などが集まって故人との最期の夜を過ごすことをいいます。
最近では夜6時頃より1時間ほどの通夜を行なう「半通夜」が行われることが一般的です。
昔は、死の確認がむずかしかったため、一晩かけて死の確認をするというような現実的な意味もあったようです。また、お線香を夜通し絶やしては行けないとのことで親族が順番で対応しておりましたが、最近は式場が防犯対策のために夜間閉鎖してしまうこともあり難しくなってきております。
通夜には親族関係をはじめとする一般会葬者も多く会葬され、喪主は弔問客の対応を行います。
告別式
葬儀と告別式は別の意味を持ちます。最近では、葬儀の読経が終わるとすぐに告別式に移ります。
葬儀は、僧侶の読経で死者があの世へ導かれ(引導)、遺族・近親者がその成仏を祈るものです。
喪主は出棺の挨拶・火葬場の同行人数の確認をおこない精進落しの手配も行います。
火葬
火葬は荼毘(だび)とも呼びます。荼毘とは、火葬をして弔うことを意味する仏教用語で、「荼毘に付(ふ)す」といった使われ方をします。
荼毘に付す前に火葬炉の前で宗教者による短い読経の後に焼香を行います。
収骨までの間は控室にて待機し、概ね一時間後に収骨を行います。
お葬式が終わったらやること
- 葬儀費用の精算
- 葬儀にかかったお金は、相続税の控除の対象になるため領収書は必ずとっておくようにしましょう。
※ 一部含まれない項目もあります
- 各種名義変更・相続手続き等行政関係の手続き
- 金融機関や自動車、不動産、株式、その他公共料金等故人が契約や所有していたものの名義変更をしましょう。
- 香典返しと挨拶状の手配
- 古くは「挨拶回り」という対面式のものが主流でしたが、現在は郵送で行う「お礼状」が主流です。郵送で香典返しを送る場合は、挨拶状を添えて送りましょう。
- 仏壇・位牌・お墓の準備
- 四十九日法要の後、納骨、お墓参りを行うのが一般的な流れとなりますので、四十九日までに仏壇・位牌・お墓の準備をしましょう。
- 法要・納骨・供養(四十九日等)の手配
- 四十九日とは仏教用語のひとつで、仏教では人が亡くなると7日ごとに極楽浄土へ行けるかの裁判があの世で行われ、その最後の判決の日が49日目となるため、命日から数えて49日目に追善法要を行います。昔は裁判が行われる7日ごとに法要を行うものとされていましたが、現在では7日ごとに法要を行うのは難しいため、最初の裁判である「初七日(しょなのか)」と、最終裁判にあたる「四十九日」のみ法要を行うというのが一般的になりました。
49日を迎えると、それまで現世に思いを残していた故人も仏様となるため、四十九日法要と同じ日に納骨を行うのが一般的な流れです。